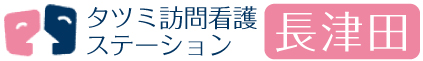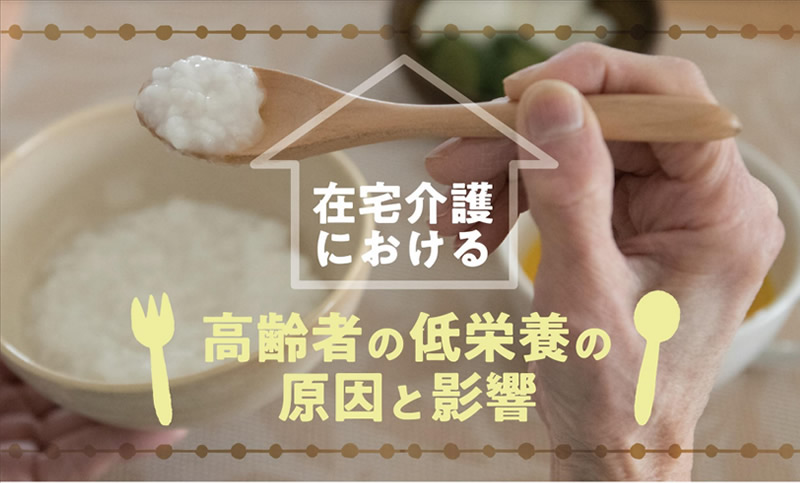訪問看護師による食支援について
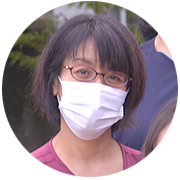 こんにちは。タツミ訪問看護ステーション長津田の古藤です。
こんにちは。タツミ訪問看護ステーション長津田の古藤です。
本日は訪問看護師による食支援についてお話しします。
訪問看護ステーションは、身体的・精神的な看護はもとより、清潔ケア(清拭、入浴介助等)や排泄管理及びケア、療養環境の整備といった「日常生活の支援」も行います。
この「日常生活の支援」のひとつが今回のテーマであるご利用者の栄養状態を保つための「食支援」です。
当然ですが、食事は生きていく上でとても大切なことです。
身体機能の低下により食べることが難しくなってきた人でも可能な限り栄養を摂取できるようにしたり、食べることを楽しんでもらえるように訪問看護が支援を行います。
訪問看護で食支援を実施するために大切なこと
訪問看護の食支援は、ご利用者の栄養状態を把握したり、口腔内の状況や摂食嚥下障害の有無を把握することが主な内容となりますが、ご利用者様の嗜好も加味した支援をすることも重要です。
訪問看護で食支援を実施するために大切なことを以下に3点にまとめました。
(1)【専門職やご家族と連携して、みんなで行うこと】
在宅療養者の食支援は専門職やご家族とで連携しながらみんなで行います。
食支援で連携する専門職は主治医,歯科医、歯科衛生士、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ホームヘルパーなどです。
在宅療養者おいて食が進まなくなる理由として、口腔内の問題(口腔内の不潔、歯の痛みや義歯の不適合、歯周病、口内炎など)があげられます。

口腔内の問題で食が進まないご利用者については、訪問歯科による評価と治療や、歯科衛生士の口腔ケアを訪問看護師が依頼するなど連携を取っていきます。
また、現在の栄養状態や食事状況の把握は、管理栄養士のアドバイスを受けながら行います。
管理栄養士から受けたいアドバイスは、適切な食材の選びや調理方法、食形態と食の提供法、栄養補助食品、食介助の方法などです。
(ちなみに最近では、在宅で訪問栄養食事指導を行っている管理栄養士も増えてきていますので、連携できるととても効果的です。)
また、日常の食事ではご家族やホームヘルパーなどが摂食・嚥下の状況を判断して介助を行わなければなりません。
ですのでご家族やホームヘルパーには、訪問看護師が状況判断の方法を指導しておくと、より正しい食事介助が行われます。
(2)【楽しんでもらって、QOLの向上につなげること】
在宅での食支援においては「食べる」ということを摂食・嚥下の視点だけで捉えがちです。
それ以外に「食事内容に変化はあるか」「誰とどこで、どんな雰囲気で食べるか」などにも目を向けて、食事を楽しんでもらったり、家族との交流の機会としてもらうように支援することも大切です。
食事を楽しむことや交流の場とすることで、食に対する意欲が沸きます。意欲が沸くと、必要な栄養を摂取できやすくなり、QOLが向上します。

QOLが向上すれば食事の摂取がしやすくなります。
この良い循環を回していくために、食べることを摂食・嚥下のみのに捉えず、楽しんでもらうための工夫をします。
工夫とひとことで言っても、いろいろな制約の中で難しいときもありますので、ステーション内でみんなで事例を共有すると良いと思います。
(3)【低栄養状態を把握する栄養アセスメントを心がけること】
ご利用者の栄養状態を把握したり評価することを栄養アセスメントといいます。
訪問看護の食支援ではこの栄養アセスメントによって低栄養状態を把握した上で行うのも効果的です。
65歳以上の在宅療養患者の「低栄養」は約36%、「低栄養のおそれ」は約34%であり、合わせて約7割の方に何らかの栄養の問題があることが報告されています。
実は、低栄養はご自身やご家族では気が付かないうちに進んでいることが多いのです。
訪問看護師が栄養アセスメントをして食支援をすることで、低栄養予防や再入院、寝たきりなどを防ぐことができます。
ちなみに訪問看護の食支援の経験が少ない看護師が低栄養状態を知るための栄養アセスメントを行う場合は「簡易栄養状態評価表」を活用すると便利です。

下記の資料は、簡易栄養状態評価表の一例です。
https://www.nestlehealthscience.jp/sites/default/files/2019-10/mna_japanese.pdf
低栄養状態になると、全身状態に影響がでますので、全身状態の観察も栄養アセスメントになります。
特に皮膚の状態(じょくそう、浮腫、乾燥の有無)、口腔状態(痛み、口臭、口腔乾燥、義歯の不具合、味覚低下の有無)、食欲不振、脱水、摂食・嚥下障害・嘔気・嘔吐、腹部膨満感・下痢・便秘などの排泄状態もみるようにします。
参考まで、「在宅介護のおける 高齢者の低栄養の原因と影響」をまとめました。
※高齢者の体の変化についてや高齢者体重減少・低栄養の原因、低栄養状態が与える影響、「低栄養」予備軍チェックリストなど載せました。是非、ご覧ください。
さいごに
訪問看護の「食支援」は、専門職やご家族と連携しながら、栄養アセスメントを心がけて、可能な限り栄養を摂取できるように工夫して、ご利用者に食べることを楽しんでもらうことです。
病院と違って、在宅療養ではお一人おひとりに合わせた食生活が可能です。
低栄養を回避しながら、QOLを向上してご利用者に食生活を楽しんでもらうよう関わっていくのも訪問看護の大きなやりがいです。
食事が楽しみで、食べることに興味がある看護師には、「在宅療養者の食支援」についてもご一緒に取り組んでいただけるとうれしいです。